これは数か月前の私たちの子供を預け入れる保育園を選ぶ基準です。
最初は教育重視→次にアクセスという感じでした。
通える範囲も想定していたので、教育とアクセス同時に重要視していました。
しかし、一遍して今は保育園に入れるところです。
私は保育園って簡単に入れると思っていたので、とりあえず教育重視で保育園を考えていました。
畑でサツマイモほりとかできる体験をしているところや、園庭に遊具があり走り回れるところなどをイメージしていて、そういったところに通わせたいな~と思っていました。
そして、小学校入るまで通うことになるので、私たち夫婦が互いに子供のお迎えできる距離などを考慮し保育園を吟味していました。
しかし、私たちは選ぶ側にはおらず、選ばれる側だったと気づいた頃には遅かった。
この記事がおすすめな人
- 保育園探し(認可)をこれから考えている人
- 男性側に保育園探しの大変さを伝えたい人
- 私と同じように保育園探しは楽勝だと思っている人
なぜ選べる側だと思っていたのか
理由は3つあります。
全ては調査不足と保育園はすぐに入れると安易に考えていたところが敗因ですが…
- 少子化という情報を鵜呑みにした
- 保育園が受け入れられる数 < 想定数だった
- ランクで自分ではどうすることもできない部分の配点が高かった
少子化という情報を鵜呑みにした

日本は子供が少ないって言われているから、当然保育園選べるかなって安直に思っていました。
確かに少子化は少子化なのですが、都市に近くなれば近くになるほど保育園も集中します。
また、通勤などのことを考えると駅に近い保育園を希望する傾向が高くなります。
しかし、皆考えることは皆同じで一極集中する結果、人気の保育園が偏る結果になります。
実は遠くの保育園も希望に入れることができるのですが、よく考えた方がいいという場合もあります。
これについては別記事で書きたいと思います。
保育園が受け入れられる数 < 想定数だった

保育園って、先生が3人ぐらいいて子供2~30人いる。
そしてクラスが2クラスか4クラスぐらいいる印象だったんですけど、思っている以上に全然少ないです。
受け入れが1歳児10人とかあったら、もうすごく多いです。
でもこの受け入れ可能人数は要確認で、下の年齢の繰り上がりが加味された人数かどうか確認が必要です。
例えば、1歳で保育園を探しているとします。
0歳児の預け入れを行っている園があったとすると、0歳児が繰り上ってくるので、0歳児に5人いたら、1歳児の受け入れは5人になるので自動的に減ります。
(こういった仕組みもわかっていなかったです。)
結論、保育園数×対応できる子供の数 < 出生数なので、選ばれる側になる。というのが今回わかっていなかったことですね。
そうならないためにも、事前調査をよくしておいた方がよいです。
ランクで自分ではどうすることもできない部分の配点が高かった

これは仕方のないことなのですが、兄弟がいる家庭や一人親世帯の人の方が配点が高くなります。(これも想定していませんでしたね)
ランクとしてはまずAランクを取る必要があるのですが、Aランクを取ったからと言って、必ず希望の園に入れるというわけではない場合があります。
理由は、保育園の数×保育園が受け入れ可能人数< 応募者数だからです。
要は需要と供給で需要過多の状態になっています。
(地域によって異なると思います)
まとめ
今回は、保育園を選ぶ側ではなく選ばれる側というお話をしました。
これは実体験で私が感じたことです。
地域によっては異なると思いますが、お住まいの地域の保育園が需要が多いのか供給の方が多いのかを調べておくだけでも違います。
私は結構、苦しんだというか、苦しんでいるのでこういった苦しむ家庭が少なくなればよいなって思います。
参考になりましたらうれしいです。
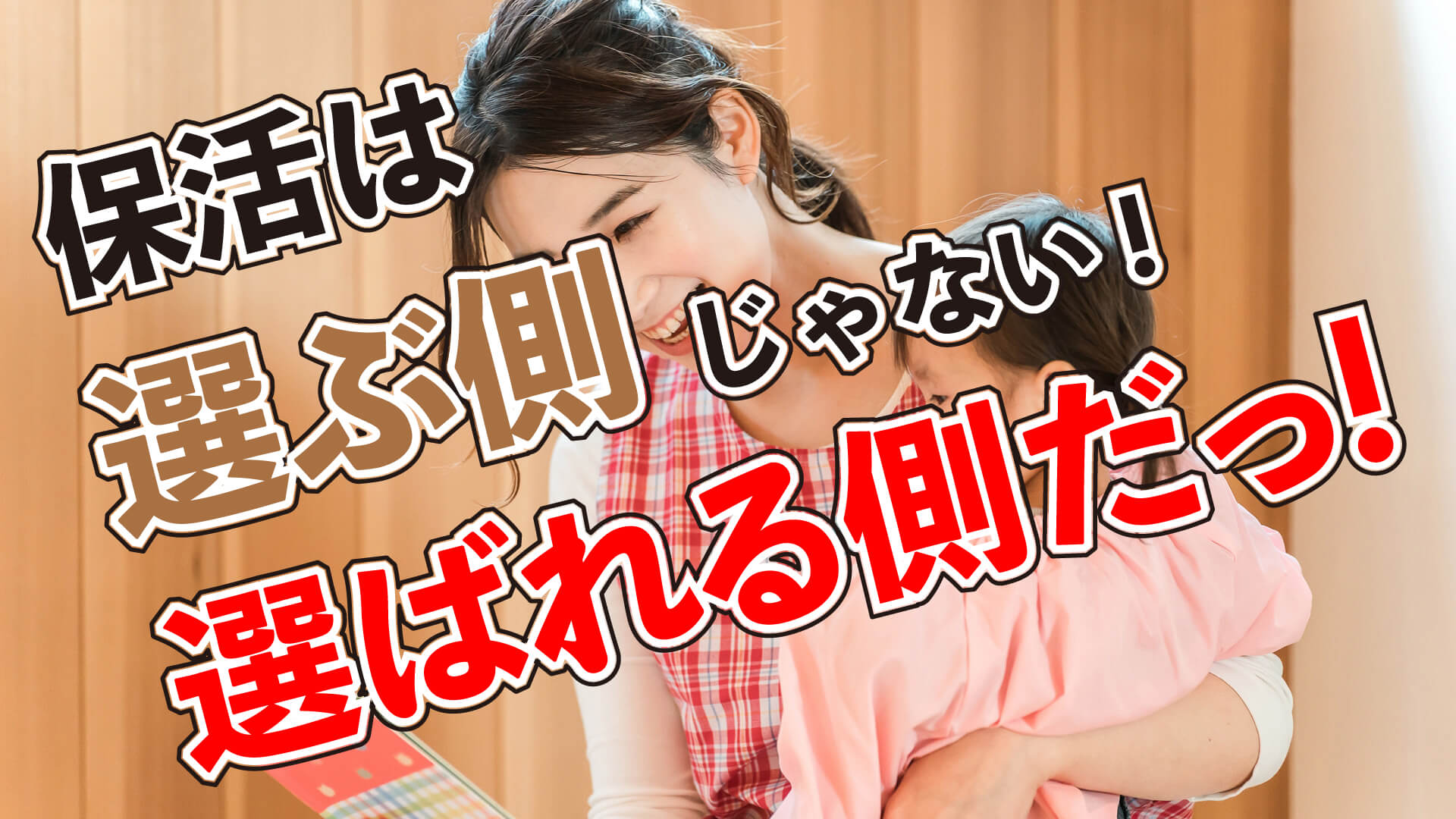


コメント